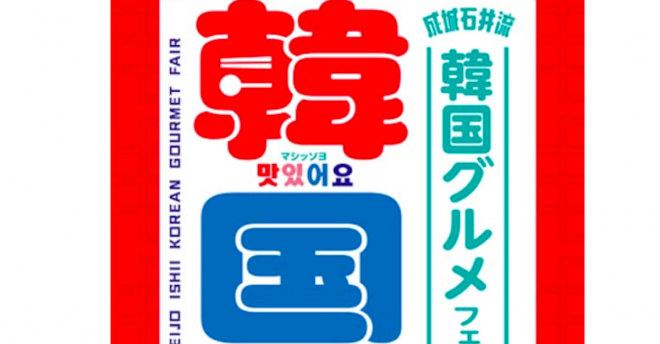-
コラム
- スーパーの裏側
- 2025/09/26 15:00
「食品ロス」が少ないスーパーの見分け方は? 元店長が明かす、“廃棄”の裏側
食品スーパーに関する疑問や消費者が知らない裏側を、創業105年にあたる2017年に倒産した老舗スーパー「やまと」の元3代目社長で『こうして店は潰れた~地域土着スーパー「やまと」の教訓~』(商業界)の著者・小林久氏に解説してもらいます。今回のテーマは「食品ロスが少ないスーパーの見分け方」。

(写真ACより) 目次
・食品の廃棄量が少ないスーパーは?
・野菜・果物には廃棄基準がない?
・廃棄が常態化するスーパー業界の事情
・食品ロス削減に取り組むスーパーの見分け方3つ
・次に変わるのは私たちの買い物の仕方食品の廃棄量が少ないスーパーは?
最近、スーパーやコンビニでは、「食品ロス削減」のために、消費期限を延長したり、AIを使って仕入れ量を調整するなど、さまざまな取り組みをしています。
お店にとって、商品を“廃棄”することは、単に利益が減るだけでなく、生産から販売まで関わった人たちを裏切る行為ともいえ、また環境問題にも加担することになります。
だからこそ、買い物をするなら廃棄が少なくなるように努めている店で食品を買いたいものですよね。そこで今回は、元スーパー社長の視点から、「食品ロス削減」に真剣に取り組んでいるお店の見分け方をご紹介します。
まず、日本全体の食品ロス(廃棄量)は、2023年度の推計値で464万トンもありました。その半分は私たち家庭の食卓から、残りはスーパーや外食・製造工場などの事業所から出ています。国民一人あたりでは、年間37kgもの食品を棄てている計算になります。想像を超える量ではありませんか?
スーパーや飲食店・製造工場で捨て、そして買ったお客さんも家で捨てる……。生活レベルの向上や企業イメージの維持のために、食べ物が捨てられています。
野菜・果物には廃棄基準がない?
ほとんどのスーパーでは、最終手段である「廃棄」の前に、何段階かの「値引き販売」をしますが、それでも売れ残った商品は“廃棄”するしかありません。
店舗では利益管理のため、「値引き商品」と「廃棄商品」をシステムに入力します。その数字が担当者の発注精度や値引き・廃棄実績として“個人評価”につながるため、なるべく値引きや廃棄をしたくありません。商品を廃棄せず、従業員が持ち帰ることは、全商品で禁止されています。そして、廃棄するにも処理費用が1トンあたり数万円発生するため、利益を圧迫していきます。
刺身、弁当や総菜、精肉など消費期限が切れた商品は廃棄一択ですが、「野菜・果物」の“廃棄基準”については法律で統一された厳密な廃棄基準はなく、各店舗やチェーンが独自に基準を定めています。
では、「野菜・果物」の“値引き~廃棄”の基準は、どう決めているのでしょうか? 主に担当者の判断で以下のポイントなどを考慮して決めます。
①入荷日
特に葉物野菜は鮮度が落ちやすく、入荷から3日程度で廃棄されています。
②見た目
陳列された野菜の形が悪かったり、一部変色しただけでもお客さんは買ってくれません。 “規格外野菜”は「農産物直売所」では人気でもスーパーに並ぶことはありません。
③再加工の可否
腐りやカビがなく、表面の変色や乾燥程度なら加熱調理に回します。
廃棄が常態化するスーパー業界の事情
また、廃棄を生むスーパーの“裏事情”もあります。
スーパーには「欠品は悪」という業界の鉄則があります。商品が品薄だとお客さんの期待を裏切る、お客さんも豊富な商品の中から選びたい。その結果、当てが外れると大量の売れ残りが発生します。夕方に値引きしても、全部は売り切れません。こうして商品の廃棄が常態化していくのです。
私の現役時代にもこの問題は深刻でした。そのため、各店舗に「生ゴミ処理機」を設置して堆肥化し、野菜を作って販売するという“循環型システム”を導入してリサイクルに努めました。
筆者のスーパー店頭に設置していた「生ゴミ処理機」(写真:小林久) 最終的には、お客さんの「家庭生ゴミ」まで集めて肥料にして、作った野菜を店で販売したほどです。私は、「レジ袋有料化」より「食品ロス削減」のほうが優先されるべき環境への取り組みだと思っています。
一方で、こんな極端な例もあります。ある人気の「農産物直売所」では、常に新鮮なものだけを並べたいとの理由で、傷みかけの野菜を一切値引きせず、すべて“寄付”に回して生産者と揉めたことがあるとか。
その後、加工業者と連携してジュースや漬物に二次利用する仕組みを整えて、ようやく落ち着いたそうです。“新鮮さ”を優先する姿勢は立派ですが、生産者からすれば「まだ食べられるのに売らずに人に譲る」ことに納得いかなかったのも当然です。食品ロス削減に真剣なスーパーの見分け方3つ
では次に、「食品ロス削減」に真剣に取り組んでいるお店を見分けるいくつかのポイントをご紹介します。
①夕方の「値引きタイム」が“毎日”あるか?
一番わかりやすいのはこれです。夕方以降に惣菜や刺し身に「値引きシール」を貼り始める店は、廃棄を減らす努力をしている証拠。逆に、値引きがほとんど見られないのに、閉店間際にほとんどの商品が棚から消えているのなら、値引きせずにすべて「廃棄処分」している可能性が高いです。野菜は開店時に「おつとめ品」として、前日の残品を値引き販売することが多いです。
②「規格外野菜」のコーナーがあるか?
形が悪いけれど味は同じ、そんな規格外野菜を安く売っている店は、ロス削減に積極的です。スーパーに限らず、見かけたら積極的に買うと、家計と農家さん、そして環境にも優しく「三方よし」です。
③フードバンクや寄付の取り組みを掲示しているか?
入口やチラシ、ウェブサイトで「食品ロス削減宣言」や「フードバンクに協力中」と掲げている店は信頼できます。大手チェーンでも、環境報告書で廃棄量を公開している企業の店舗を選ぶのも一つの方法です。
次に変わるのは私たちの買い物の仕方
「食品ロス削減」は、スーパーだけでなく社会全体の課題です。
お店が値引きや規格外野菜の販売に取り組むのは、決して簡単ではありません。だからこそ、私たちがそうした商品を選んで買うことが、お店を支える力になります。「値引きシール」が貼られた商品を買うことも、恥ずかしいことではなく、立派な「食品ロス削減」への貢献です。
一人ひとりの小さな選択が積み重なれば、まだ食べられる食品はゴミではなくなります。スーパーが努力して変わっている今こそ、次に変わるのは私たちの買い物の仕方なのかもしれません。◆関連記事
- RELATED ARTICLES
-
アクセスランキング
- ACCESS RANKING
2026.02.16.6:00更新スーパー
- SUPERMARKET
【成城石井】初の韓国グルメフェア、新商品38品が登場! 647円「ドバイチョコ風ケーキ」など
新商品
- NEW
「ビジュアルかっこよすぎ!」【Netflix】初コラボ、セブン「金のマルゲリータ」食べたら「生地にびっくり!」
レシピ
- RECIPE
「ムフゥ……」おいしすぎてため息!【明太クリームつけそうめん】夏が終わるまでに食べてほしいレシピ
プロが解説
- PROFESSIONAL
収納のプロが教える「捨てない片付け」アイデア6! 使い方を変えるだけでリビングすっきり【ビフォーアフター】