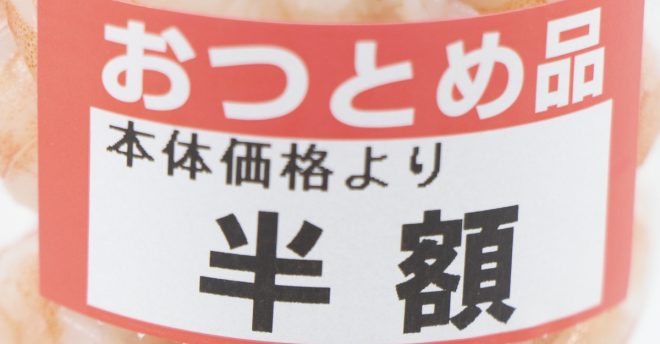-
スーパー
- スーパーの裏側
- 2025/04/25 15:00
「ロピアは強い!」近隣スーパー2店が撤退――「大容量・低価格」への対抗策は「中高齢・単身者」?

ロピア(写真:スーパーマーケットファン) 食品スーパーに関する疑問や消費者が知らない裏側を、創業105年にあたる2017年に倒産した老舗スーパー「やまと」の元3代目社長で『こうして店は潰れた~地域土着スーパー「やまと」の教訓~』(商業界)の著者・小林久氏に解説してもらいます。今回のテーマは「ロピアの出店でローカルスーパーは潰される?」。
目次
・ロピアは買い物というより「イベント」に近い体験
・【ロピア】3つの強さと、拡大路線の速さ
・ロピアに隣接する地域スーパー、売り上げアップのワケ
・既存スーパーがロピアと共存するための条件
・「ロピアは強い!」これは紛れもない事実ロピアは買い物というより「イベント」に近い体験
今、スーパー業界で最も勢いのあるチェーンといえば、間違いなく「ロピア」の名が挙がるでしょう。関東圏から全国へと拡大を続けるそのスピード、そして「日本版コストコ」とも呼ばれる独自のスタイルで、業界の勢力地図を塗り替えつつあります。
一歩店内に入ると、ボリューム満点の精肉や鮮魚、「映える」惣菜やデザート類がずらりと並び、来店客の購買意欲を刺激します。価格のインパクトも強烈で、買い物というよりエンタメ感のある「イベント」に近い体験ができるのが、ロピアの大きな魅力です。
全国から出店のラブコールが鳴りやまないロピアですが、もしこんな強力なスーパーが近隣に進出してきたら、既存のスーパーはまさに死活問題です。メディアやSNSによって、すでに認知度が高いロピアは、開店と同時に地域から年間40億円ものシェアを奪うことは明白です。
実際、私が住む山梨県でも、2022年12月にロピアが甲府駅前に出店したことを機に、近隣のスーパー2店舗が撤退し、現在も空き店舗のままです。いくら自由競争とはいえ、ローカルスーパーが淘汰されるのを目の当たりにすると、もはや日本中どこでもひとごとではいられません。
【ロピア】3つの強さと、拡大路線の速さ
まずは、ロピアの強さを整理してみましょう。
① 家庭単位の「まとめ買い」に特化したボリューム戦略
「コストコ」並みの大容量ではなく、日本の一般家庭が使い切れるサイズで「お得感」を演出しているのが、ロピアの絶妙なところです。大きすぎて持て余す心配がない分、気軽にまとめ買いができます。
②生鮮部門の圧倒的なコストパフォーマンス
もともと精肉店からスタートしたロピアは、「精肉」のコスパの高さに定評があります。さらに、鮮魚や青果も各店舗の担当者に仕入れの裁量が与えられており、「店舗全体がひとつの商店街」というコンセプトです。
③エンタメ性の高い売り場演出とSNS映えする商品展開
平台での大量陳列や目を惹く大きな商品POP、店内モニターやBGMを駆使した売り場はエンタメ感満載です。また、SNS映えする商品を次々と開発して、購買意欲をかき立てる空間づくりに余念がありません。
これらは、ランニングコストの高い小規模店や、「売り」のない平均的なスーパーでは、とても太刀打ちできません。
ロピアがヨーカドーなど大型店の空き店舗に出店したり、M&Aを進めたりするのは、コストの抑制や独自の仕入れルートを築くためです。こうした、ほかに例を見ない拡大路線の速さを考えたとき、「同じ土俵では勝負にならない」というのが現実なのです。
ロピアに隣接する地域スーパー、売り上げアップのワケ
しかし「ロピアが出店してきたら、既存スーパーは潰されてしまうのか?」といえば、そうではない事例もあります。
たとえば、2024年11月にロピアが北海道・屯田(とんでん)地区に初出店した際、そのすぐ隣にあった地域密着型スーパー「北海市場」は、逆に売り上げが前年比で2〜3割もアップしました。
もちろんロピアの開店効果で、より多くのエリアから来店客があったとはいえ、この増加率は想定外といえます。
北海市場によれば、ロピアが「安くて大容量」に特化しているのに対して、「良いものを、ちょうどいい量」で対抗したとのこと。
生活スタイルが違うお客さんをしっかり取り込んだ結果、「ロピア=週末ファミリー向け・北海市場=日常の買い物向け」という見事なすみ分けができたのです。
北海市場に限らずロピアが出店しても生き残っているスーパーは、例外なく「価格」で対抗せず、「価値とサービス」でお客さんを呼び込んでいます。
既存スーパーがロピアと共存するための条件

大容量がウリのロピアのティラミス(写真:スーパーマーケットファン) では、私自身の経験と実例を踏まえ、既存スーパーがロピアと共存し、生き残っていくための条件を整理してみます。
まずは、「週末のまとめ買い目的」ではなく、小回りの利く「日常の買い物」を支える存在になることです。
「大容量・低価格」ではなく、あえて「少量パック・高品質・適正価格」を強化した売り場構成にして、ロピアがターゲットとしない中高齢者・単身者の生活スタイルに徹底的に寄り添うこと。
次に、既存店の強みである地域住民・生産者・学校とのつながりを武器に、積極的に「朝市」や「◯◯マルシェ」「フリマ」「駐車場でのイベント」などの販促を通じて「地域の拠点」になること。
最後に、柔軟な決済手段を整えることです。ロピアでの支払いは、現金と自社アプリのプリペイド払いのみで、一般の電子マネーやクレジットカードは使えません。この点に不満を抱くお客さんは少なくないため、多様な決済手段を用意することは大きな差別化ポイントになります。
「ロピアは強い!」これは紛れもない事実
確かに、ロピアが近隣に出店すれば、既存のスーパーが苦境に立たされる可能性は高いでしょう。特に経営資源が乏しい個人経営のスーパーでは、その影響は深刻です。
「ロピアは強い!」これは紛れもない事実であり、勢いがすぐに衰える兆しも見えません。
とはいえ、その急成長を支えるメディア戦略や、大容量・低価格の商品戦略に正面から対抗するのは危険です。ましてや価格で張り合えば、体力を消耗するチキンレースに陥るだけです。
業界では口には出さなくても「新たなスーパーが出店する=既存店を潰しにかかる」ことが常識であり、「共存共栄」は現実には難しいのです。
だからこそ、既存スーパーは決してロピアと同じ土俵に上がるのではなく、自店の特色を生かした「別の土俵」で戦うことが求められます。「安いから選ばれる店」ではなく、「この店が好きだから通う」という信者(ファン)が多い店は必ず生き残れます。
「勝ち負けではなく、どう生き残るか?」、私はそれこそがロピアを迎え撃つスーパーが目指すべき道だと思います。
-
アクセスランキング
- ACCESS RANKING
2026.02.05.18:00更新スーパー
- SUPERMARKET
大阪ローカル【スーパーナショナル】、人気の214円「焼き餃子」食べて納得「これおいしい!」
新商品
- NEW
「ビジュアルかっこよすぎ!」【Netflix】初コラボ、セブン「金のマルゲリータ」食べたら「生地にびっくり!」
レシピ
- RECIPE
【鶏むね肉だけ】冷凍のまま焼いて「パッとジュッと」214円で完成! 頑張らない「料理の素」レシピ
プロが解説
- PROFESSIONAL
収納のプロが教える「捨てない片付け」アイデア6! 使い方を変えるだけでリビングすっきり【ビフォーアフター】